![]()
妙福寺トップページ > 妙福寺PRESS > 住職日記 > 立秋と仏教──季節の”あわい”を感じる

2025/08/07
立秋と仏教──季節の”あわい”を感じる
まだまだ蝉が鳴き止まず、熱帯夜が続く。それでも暦の上では「秋」が始まる──そんな立秋に、仏教と和歌、そして自然の声から、少し涼しくなる話を。
立秋。
毎年8月7日ごろ、暦の上ではこの日から「秋」に入ります。
けれど、外を歩けば汗だく。日差しは鋭く、蝉の声は容赦ない。
「どこが秋なんだ」と、つい文句のひとつも出たくなる時期です。
けれど、仏教の視点から見れば、この「暦の先取り」には深い意味があります。
仏教の基本的な思想のひとつに「諸行無常」があります。
すべては変わりゆく。
そしてその変化は、いつも目に見えるかたちではなく、静かに、音もなく、訪れることが多いのです。
たとえば、『古今和歌集』巻四にある藤原敏行の歌──
秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる
これはまさに、「立秋の日」に詠まれた和歌です。
秋が来たとはっきり目には見えないけれど、風の音にその気配を感じた。
ここには、視覚ではなく聴覚で季節の移ろいをとらえる、日本人の繊細な感性が息づいています。
まさに、仏教が大切にする「気づき(サティ)」の心です。
日常の中にある変化、目には見えないけれど感じ取れるもの。
それに耳を澄ますことは、心を整えるひとつの実践でもあるのです。
仏教では、すべての現象が移ろいゆく「無常」であることを受け入れ、
それを苦ではなく、むしろ今ここを大切にする智慧として説きます。
暑さのなかでふと吹いた風、蝉の合間に混じる秋の虫の声。
立秋は「残暑」の始まりであり、同時に「秋の入口」です。
暑さと涼しさの“あわい”を通り抜ける、心の風を感じていきましょう。
その「小さな変化」に気づくこと。
それこそが、仏教の教える“心の涼”なのだと思います。
よろしければ下記の記事もお読みいただけると嬉しいです。
シリーズ「マインドフルネスと暮らし」──こころの"休日"をつくる
次の記事へ
- 2025/08/07 立秋と仏教──季節の̶…
- 2025/06/15 アンディ・ウォーホルの…
- 2025/02/02 選択の少欲知足
- 2024/10/26 「旬」
- 2023/04/12 【くつろぎの瞑想】
- 2026年1月 (2)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (1)
- 2025年2月 (2)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (2)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (1)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (3)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (3)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (4)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (5)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (2)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年2月 (2)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年9月 (2)
- 2013年8月 (2)
- 2013年7月 (1)
- 2013年5月 (4)
- 2013年3月 (2)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (2)
- 2012年12月 (2)
- 2012年11月 (2)
- 2012年10月 (4)
- 2012年9月 (2)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (4)
- 2012年6月 (3)
- 2012年5月 (2)
- 2012年4月 (3)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (3)
- 2012年1月 (3)
- 2011年12月 (3)
- 2011年11月 (4)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (5)
- 2011年8月 (4)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (1)
- 2011年5月 (8)
- 2011年4月 (13)
- 2011年3月 (14)
- 2011年2月 (3)
- 2011年1月 (3)
- 2010年12月 (7)
- 2010年11月 (7)
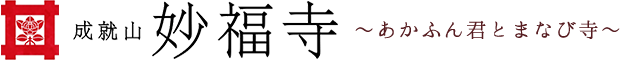
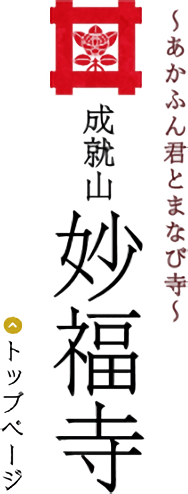


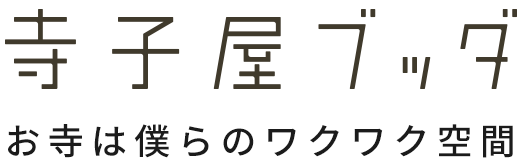

住職日記 | Comments(0)