![]()
妙福寺トップページ > 妙福寺PRESS > 妙福寺おすすめ本 > 「名前のない関係」に生きる勇気──『ババヤガの夜』と“空”のレッスン

2025/07/28
「名前のない関係」に生きる勇気──『ババヤガの夜』と“空”のレッスン
人は、なぜこれほどまでに関係性に「名前」をつけたがるのでしょう。
友人、恋人、夫婦、親子、同僚──。
関わる人を何らかのカテゴリに当てはめることで、安心しようとするのは人間の習性なのかもしれません。
けれど、そのラベルの内側で、息苦しさを感じたことはありませんか。
「こうあるべき」という期待が、私たちの言葉にできない“心地よさ”や“しっくりくる距離感”を否定してしまうこと。
今回、日本人初のダガー賞を受賞した王谷晶の小説『ババヤガの夜』は、その「名前のない関係性」の可能性をそっと照らし出してくれる物語です。
ラベルの外側に広がる世界
『ババヤガの夜』の登場人物たちは、どこか壊れやすく、孤独で、それでも誰かとつながりたいと願っています。
けれど、そのつながりは「友達」「恋人」といった言葉ではうまく説明できない。
社会は、こうした関係性を落ち着きなく見つめます。
「つまり何なの?」と定義を迫り、「どんな関係?」と聞きたがる。
しかし、王谷晶はこの物語の中で、ラベルの外側にあるもの──
言葉で定義できない関わりが持つあたたかさ、自由さを描きます。
夜の静けさのように、柔らかく、しかし確かに存在する“誰かとの距離感”。
読後、あなたの身近にも思い当たる関係があるかもしれません。
言葉が固定するもの、奪うもの
男に見えるものと女に見えるものが一緒にいれば、すなわちそれは夫婦と見られる。カタにはまった世の中ほど騙しやすい。一度カタにはまったふりをしてしまえば、誰も新道と尚子が本当は何なのか、どういう人間なのか、気にかけない。
ババヤガの夜 文庫版 p178
登場人物が語る通り、私たちの認識にはクセがあります。
それは自分が経験した事がなかったり、認識できないモノゴトを、自分が理解できる範囲のモノゴトに変換し、既存のカタにはめて理解することです。
仏教の「空(くう)」という教えは、「すべてのものごとは固定的な実体を持たず、常に変化している」という考え方で、それは自分の認識や、その認識によって与えた名前やラベリングは固定的ではなく、時間や状態、関係性によって常に変化する、だからその認識やラベリングに縛られず、常に変化を観察しなさい、という教えです。
例えば、ここに2本の棒があります。
Aの棒は5cm
Bの棒は10cm
Aの棒を認識する為に、名前をつけます。
「短い棒」
となると、Bの棒は
「長い棒」ですね。
しかし、ここでCという15cmの棒が並んだらどうでしょうか。
A「短い棒」
B「中くらいの棒」
C「長い棒」
ここでBのラベリングに変化が訪れました。
さらにD,E,Fと増えたら、さらに変化していきます。
それぞれの棒にラベリングした「〜〜な棒」という属性は常に変化をして固定的ではありません。
このように、目で見て比較できるものは、一度ラベリングしても張り替えやすいですが、目に見えないものは一度ラベリングすると、なかなか変化に気がつけず、決めつけでモノゴトを捉えがちになります。
人の関係性も同じです。
「この人は友達だ」と言葉でラベリングした途端、私たちは無意識に「友達らしい」ふるまいを期待し、「友達らしくない」行動に傷つきます。
けれど、人も関係も絶えず揺れ動くもの。今日の心地よさが、明日も同じとは限らない。
言葉は便利です。
でも、言葉は同時に、ものごとの流動性を封じ込めてしまうこともある。
固定観念に縛られず、変化を受け入れる姿勢こそが“空”の実践なのです。
名前がないから、自由になれる
ライフスタイルにも同じことが言えます。
「会社員」「母親」「フリーランス」など、社会が用意したラベルは数多くあるけれど、そのどれもがあなたを完全に説明できるでしょうか。
「何者なのか」という問いに答えられない不安。
でも、それは実は自由の兆しです。
ラベルがない状態は、どこにでも動けるし、誰とでも新しい関係を結べる余白を持っているから。
『ババヤガの夜』の登場人物たちがそうであるように、私たちも「名前のない関係」に身を置いていい。
そして「名前のない自分」でいる時間を、もっと大切にしていい。
言葉に縛られず、変化に寄り添う
“言葉にできるものだけが真実じゃない”と気づくこと。
それは関係性に限らず、仕事、暮らし、人生観すべてにおいて当てはまります。
肩書きやステータスに頼らず、「いまこの瞬間、どんな関係が心地よいか」「どんな働き方が自分らしいか」を感じ取る。
そこから始まる生き方は、社会の型にはまらないぶん、不安もあります。
でもその不安の先にこそ、言葉にならない深い満足感が待っているのではないでしょうか。
次の記事へ
- 2025/07/28 「名前のない関係」に生…
- 2022/12/05 『昔話の深層』河合隼雄
- 2022/09/29 『良薬ナル読書ハ百ノ医…
- 2021/06/30 【あんなに あんなに】…
- 2021/05/22 【丁寧な暮らしをする餓…
- 2026年1月 (2)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (1)
- 2025年2月 (2)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (2)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (1)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (3)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (3)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (4)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (5)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (2)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年2月 (2)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年9月 (2)
- 2013年8月 (2)
- 2013年7月 (1)
- 2013年5月 (4)
- 2013年3月 (2)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (2)
- 2012年12月 (2)
- 2012年11月 (2)
- 2012年10月 (4)
- 2012年9月 (2)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (4)
- 2012年6月 (3)
- 2012年5月 (2)
- 2012年4月 (3)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (3)
- 2012年1月 (3)
- 2011年12月 (3)
- 2011年11月 (4)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (5)
- 2011年8月 (4)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (1)
- 2011年5月 (8)
- 2011年4月 (13)
- 2011年3月 (14)
- 2011年2月 (3)
- 2011年1月 (3)
- 2010年12月 (7)
- 2010年11月 (7)
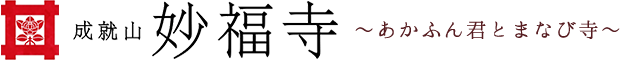
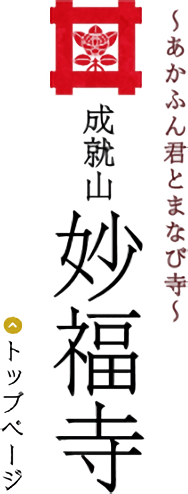


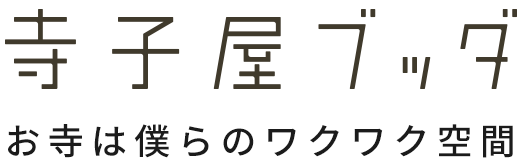

妙福寺おすすめ本 | Comments(0)